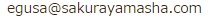取材に関して
- 直接お問い合わせください
-
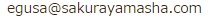
まで直接お問い合わせください。
- 1 出版を始めようとしたいちばん大きなきっかけは?
- きっかけは、社会人になって出版社の営業や、関東で新聞記者をやってきた中で、地元に戻って就職したIT企業が全く肌に合わず、これまでの人生で一番というくらいの挫折を経験したことがいちばん大きい。パソコンだけに向き合う仕事よりも、取材したり、人と関わってきたこれまでの仕事の楽しさや奥深さがどうしても捨てきれなかった。が、いざ出版社に就職しようとも、地元には出版社がほとんどなく、以前出版企画を持ち込みとても親切に対応してくれた出版社の社長に電話をかけ、「アルバイトでもいいから雇ってほしい」と直談判したものの、「無理」と言われた。「だったら出版社を作りたい」と相談したら、「絶対やめなさい」。それでも食い下がり、「やっぱり、自分一人でもいいからやってみたい」と突っ走る何も知らない私に半ば呆れかえり、出版業の厳しさを教えてくれた上で、「やるなら、応援はするよ」と後押ししてくれたことで動き出すことができた。
- 2 始めようとした頃、出版界の危機に気づいていましたか。
気づいていたとしたら、どんなふうにとらえていましたか。
- 気づいていた。
まず出版社の体質。2006年と08年に書いた2冊の本は、ただただ本を出して終わり…そう感じていた。この頃は、なんでこんなに短時間で強引に本を作って、量産するのだろうかと不思議に、そして不安に思っていた矢先の1年後、09年に2冊目の本を出した出版社は倒産した。また、原稿だけ書いて、3年以上も企画が宙に浮いたままの状態のものもあり、やがて自然消滅。出版社と編集者のモラルの低さに怒りを覚えたこともあった。冊数を刷っただけで、結局は必要な人に本は届くこともなく、悲しい思いをした。そして、流通面。当時は「取次」という存在を理解していなかったが、本の流通は、はたしてこれでいいのだろうかと漠然と思っていた。
一冊の本にはたくさんの人がかかわり、本来は人と人とが向き合って作っていくものなのに、なぜ機械的なのだろう? なぜ「取次」が必要なのか? 直接読者に届けることはできないのか? 出版社の存在とは一体なんだろう? と日々悶々と考えていた。毎日のように書店を見て歩くと、本が入っているであろう大量の箱が開けられないまま放置されていた。きっと、開けられずに返本されるのかもしれないと思った。書店員も、流れ作業みたいな仕事の繰り返しで、どことなく表情が疲れ切っているように見えた。なんか全ての構造がいびつで、無理があるんじゃないのか。これでは、作家が出版社や取次を介さずに、直接読者と取引をする時代が来るのかもしれないとも思っていた。
自分が子供の頃に父とよく行った桜山にあった日進堂書店がなくなった頃、本が一気に遠い存在になったことを覚えている。2000年代には地元の小書店が一気に無くなり、それだけでもう出版界の危機は痛いほど感じていた。
- 3 始めて1年半、手ごたえは?
- 手ごたえは、正直わからない。あるとも言えないし、ないとも言えない。
ただ、中日と朝日新聞で一人出版業の活動を紹介してもらい、読者から本の感想が寄せられたり、著者も完成した本を喜んでくれたり、サイン会では直接読者の顔を見て触れ合うことができた。一冊を売ることがどれほど難しいことなのかを知って身が引き締まる思いがした。
本の制作過程は長く苦しい道のりだけれども、それを上回る嬉しい瞬間がだんだん増えてきていることは確か。書店が売りたいと思ってはじめて出荷されるトランスビューの「注文出荷制」を採用することによって、出版側も無理をする必要はなく、版元の規模やペースに合わせた本づくりが可能となり、書店の粗利も改善されつつある。出版側も、その本を必要としてくれる人に、一冊一冊地道ではあるけれども、確実に届き始めていることを実感できることもやりがいにつながっている。地元の出版社だからと応援してくれる書店もあり、店頭に飾られた大きなPOPを見て、あまりの嬉しさに感動して泣いた。一人出版業だけど、決して一人ではないんだと思うと頑張っていけそう。そんな意味ではとても恵まれているし、有難いことなのだとも。
- 4 今後の展開は?
- 「人」がすべて。これからも、地元で頑張っている人にスポットが当たる本を企画していき、名古屋からの情報発信と手作り感を大事にしていきたい。
既刊本は、作って終わりではなく、時間がかかってでもいいので、ていねいに一冊を読者に届けていきたいと思っている。
本は記録としても後世に残していく大事なもの。これまで本を書いたことで学んだこと、出版営業や新聞記者の経験から、
出版業の原点に立ち返り、出版の目的に合わせた本づくりにも力を入れたい。
※「なごや文化情報」のインタビューより
桜山社について